中央快速線ではお茶の水駅で信号機故障が発生したため、午前6時50分ごろから運転を見合わせました。平日(木曜日)朝の通勤時間帯でしたので、大きな混乱が発生しました。並走する中央総武線も遅れが発生し、JR東日本では周辺の各鉄道会社への振替輸送を実施していました。
午前7時48分までは運転再開の予想時間を発表できない状況でしたが、同刻に係員が現地に到着、7時50分には運転再開見込みを午前8時と発表しました。そして、午前7時55分に運転を再開しています。
とすると、故障が発生してから係員が現地に着くまでは約1時間、復旧作業は数分、その後、安全確認を実施して運転再開という経過を辿ったことになります。係りの方が近傍で待機されていれば相当に復旧までの時間を短くすることができて、何万人もの人に影響を与えることも無かったかもしれません。仕方がなかったことなのか、再発防止策が必要なのかは、JR東日本でぜひ振り返りを進めてほしいと思います。

使用者側の立場から見ると、設備に故障が発生することは致し方ないことと割り切ったとしても、重要なインフラである以上、復旧までの時間をいかに短縮するかは大きな命題だと思います。特にお茶の水駅といえば都心の各線が乗り入れるターミナル駅ということもあり、もう少し係りの方が駆けつける時間を短くできるよう、事前に策を立てておくことができたのではないかとも思います。
JR東日本は、みどりの窓口を急速に減らして、残った窓口で長蛇の列ができるなど、行き過ぎた合理化のために問題が発生する事象が発生しています。JR東日本の2024年のグループレポートを見ると「駅係員の配置の平準化」という記載があります。
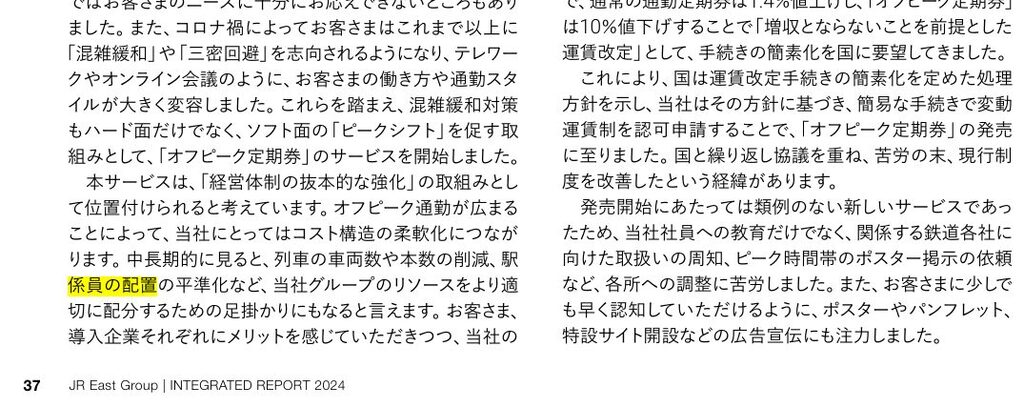
今回の事案も保線をする方の配置について点検する必要があるかと思います。
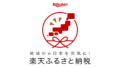

コメント