さくらインターネットが7月28日に2026年3月期通期(2025年4月1日〜2026年3月31日)の連結業績予想を下方修正することを発表しました。4月28日に公表した時点から下記のように下方修正しています。
- 売上高 404億円→365億円
- 営業利益 38億円→3億5000万円
- 経常利益 34億円→4億円
下方修正の原因は継続を見込んでいた生成AI向けの大型案件終了のためとしています。
下方修正の内訳としては、GPUインフラストラクチャサービスの売上予想を158億円から85億円に引き下げています。逆にグループ会社の案件獲得などで、その他のサービスの売上予想を57億円から87億円に引き上げています。
この発表を受けて、2025年7月29日の東証では、さくらインターネットの株式に値がつかず、ストップ安という状態になっています。さくらインターネットの株式を持っていた人にとっては、寝耳に水の発表でとても驚いたのではないでしょうか。
さくらインターネットも4月28日の発表段階から、まだ3ヶ月も経っていない間に、今年度の売り上げで73億円にもなるビッグユーザーを継続利用してもらえなかった本質的な原因はどこにあったのでしょうか。4月28日の段階で、さくらインターネットがどこまでリスクとして認識していたのかどうかも投資家保護の観点からは気になります。
一方で、さくらインターネットは本日付けのニュースリリースで、気象庁が一般競争入札で公募していた「ハイパフォーマンス・コンピューティング・クラウドサービスの提供」に関して、落札額約25億円で契約を締結したことを発表しています。契約期間は2026年1月30日から2030年3月31日までとなります。
また、8月には新型GPUの「NVIDIA B200」の提供を開始するとしていますが、これらの準備したインフラを利用する顧客をどこまで集めることができるか、莫大な投資コストに見合う売り上げを立てることができるかどうかが、今後の利益改善に向けての鍵になると思います。


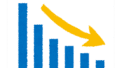
コメント