日経クロステックでパーソナルコンピューティングの40年という特集が組まれています。第一回として「UNIXを源流としたOS、8ビットCPUの登場でパソコンの自作が始まる」という記事があったので読んでみました。
この記事の中で最も驚いたのは、創業間もない米国の新興企業であったIntel社に1969年、世界初のCPU開発を委託したのは、日本にあるビジコンという会社であったという事実です。
手回し式計算機の会社
ビジコンという会社を知らなかったのですが、1944年に手回し式計算機の製造販売を手掛ける会社「富士星計算機製作所」として設立されて、1970年にビジコン株式会社に商号変更しています。
手回し式計算機から、1960年代には世界初の電卓と呼ばれている「アニタ・マーク8」の日本への輸入をしたことで電子計算機との関わりを持つようになり、1966年に磁気コアメモリを採用したビジコン161で電卓市場に参入しました。
電卓の輸入販売という事業形態から自社で磁気コアメモリを使った自社開発の電卓製造まで飛躍できたのは何が鍵だったのかとても興味があります。(三菱電機のコンピュータの販売、保守を通して、電子計算機の知識、素養を持った社員も多く、ストアードプログラムやチップの開発などの発想が生まれたと電卓博物館というサイトに記載がありました)
電卓からCPU製造まで
その上、ストアードプログラミング方式の電卓を発売することを発想して、1969年にIntelに対して電卓用のCPU製造を委託するまでに至ったのは、凄いことだと思います。
その後の電卓市場の競争激化、円安による為替差損、三菱電機のコンピュータ市場からの撤退などの影響があり、1974年に倒産しています。
ビジコン社からの依頼で作られたIntelマイクロプロセッサ「4004」ですが、さらに8ビットのCPUの発売へとつながっていきました。
このような創造的な仕事を成し遂げたビジコンという会社については、もう少し調べて勉強したいと思います。
【2025年9月11日追記】
盛者必衰
インテルは1990年代半ばから2000年代にかけては、家庭用パソコンにはインテルのCPUが入っていることが当たり前というほどに非常に成功していました。しかし、2010年代から徐々に変化が訪れました。例えば、スマホ向けにもINTELとマイクロソフトの組み合わせで進出しようと試みましたが、iOSやandroidには太刀打ちできませんでした。一番大きなインテルの判断ミスは2000年代後半にAppleがIntelにスマホ用CPUの供給を依頼した際にIntelは断ってしまったことだともいわれています。スマホという分野のその後の伸びについて認識が不足していたのか、Appleとは組まずにマイクロソフトと組もうと思っていたのか、断った背景に何があったのかは分かりません。
2010年代後半になりAIが注目され始めた時に、それまではGPUが得意であったエヌビディアの技術に優位性があると脚光を浴びましたが、残念ながらIntelはAIブームに乗り遅れてしまいました。さらに2020年代には最も得意分野であったはずのパソコンやサーバー用のCPU分野で不具合や性能不足といった問題が続いて、第二位のAMDにシェアを奪われています。
最も象徴的な変化は2024年にマイクロソフトから発売されたSurfaceというパソコンにSnapdragonというクアルコム社製のCPUに置き換わったことでしょう。
会社の寿命は40年というジンクスもありますが、インテルが今後の環境変化を乗り切っていくことができるかどうかは非常に注目されています。
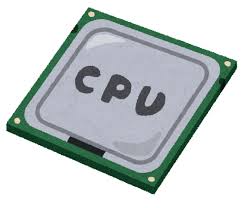

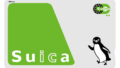
コメント